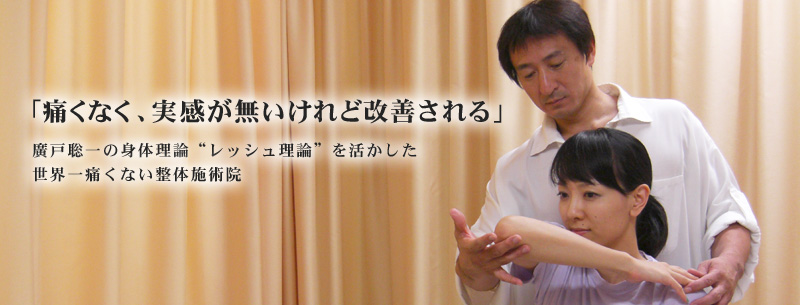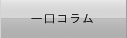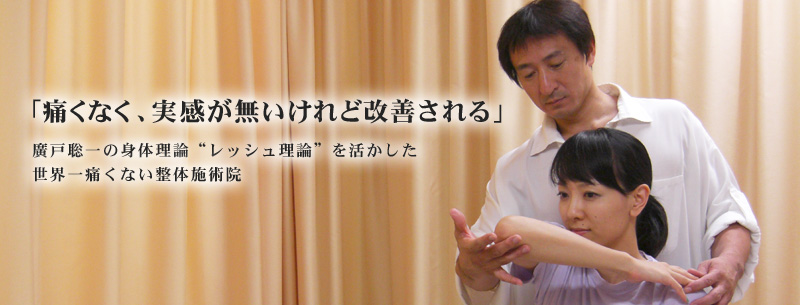「柔軟性と可変性」
皆さん、こんにちは。
レッシュ理論に於いて、軸が出来たことの効果として
「柔軟性が増す」
というものがあります。
ひらたく言えば、身体が柔らかくなる、ということです。
これは、軸が出来たことにより骨格で身体の安定性を獲得出来たが故に余計な筋緊張が抜けることがその理由です。
では、その逆(厳密に言えば逆ではありませんが…)「柔軟性がある人は常に軸が出来ているのか?」という事を考えてみす。
一般的に身体の硬軟を測る一つの指標として、
「立位若しくは長座からの前屈率」
が挙げられます。
確かに手が床や爪先に届くか否かでその得手不得手は実感出来ると思いますし、最も多く用いられる計測法ではあります。
しかし、それは人間の動作の一つであって、全てがそれによって決定付けられることではありません。
例えば、股関節で見れば、内外転、屈伸、内外旋という方向性を持っています。
また、三次元的かつ多角的に様々な箇所がお互いに連動し合うスポーツやダンスでしなやかな動きが、前屈が得意という条件だけでは到底不可能ですし、たとえ前屈が苦手でも滑らかな身のこなしを行う方もたくさんいらっしゃいます。
この様に考えると、
「前屈率=柔軟性」とは必ずしも言い切れませんし、前屈が得意な方が軸を作るのが上手いかということも然りとなります。
立位や座位で軸を作る場合、5つあるポイントのうち3つ以上を垂直に揃えますが、立体である人体でこの動作をきれいに行う為にはタイプにかかわらず、体幹部を柔らかく動かす必要があります。
所謂、背すじを伸ばして胸を張った「気をつけ」の姿勢では軸は作れませんし、脳の安定感は得られないのです。
ですので、レッシュ理論における柔軟性とは、
「肋骨(体幹部)をいかに可変させられるかの度合」
と定義出来るかと思います。
脱力した状態から軸を作り、さらに安定感を得たうえで更に柔軟性が増したり向上するのです。
肋骨や体幹部が硬い人と柔らかい人の安定感を、ビルなどの建築物で例えれば前者は「耐震構造」、後者は「免震構造」とイメージが重なるかもしれません。
全体が揺れない(動かない)様に固めてしまうか、揺れ自体を受け流せるような柔らかい態勢をとるのか、の違いと表現出来るかと思います(厳密な耐震、免震の定義はわかりませんが)。
今まで言われてきたいい姿勢や柔らかさでは無く、いかに肋骨が最も柔らかく動かせる態勢を整えるのか、またそれが動く為の準備が整った「いい姿勢」であることをより多くの方に認識して頂きたいものです。
|